船井総研あがたFASです。今回は食品業界のM&Aで使われる譲渡スキームについてお伝えしたいと思います。
「まだ先のこと」と考えているうちに、選択肢が狭まってしまうかもしれません。今年以降のさらなる採用難・競争激化に備え、今から「攻めの出口戦略」を検討しませんか?具体的な検討ツールのダウンロードや、専門家への出口戦略の相談を通じて、納得感のあるリタイアへの準備を今から始めることができます。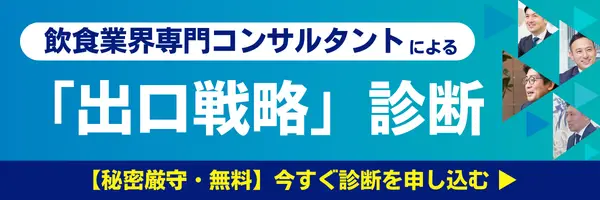
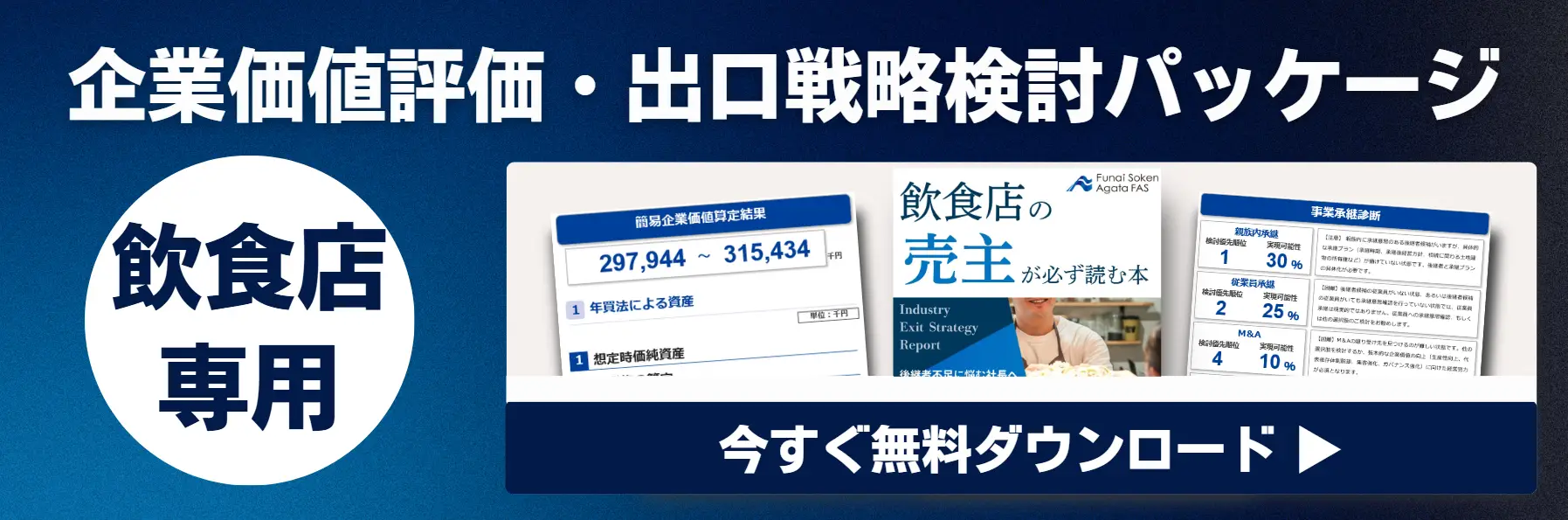
食品業界:主なM&Aスキーム
まずは一般的にM&Aの際に用いられる主なスキームは下記の4つとなります。
1. 株式譲渡
概要: 買収対象企業の株式を譲渡することで、経営権を取得するスキームです。
メリット
- 手続きが比較的簡単で、時間やコストを抑えられる
- 買収対象企業の資産や負債を包括的に引き継げる
- 買収後の経営統合がスムーズに進めやすい
デメリット
- 簿外負債や偶発債務などのリスクも引き継ぐ可能性がある
- 買収対象企業の株主との交渉が必要になる
2. 事業譲渡
概要: 買収対象企業の事業の一部または全部を譲渡するスキームです。
メリット
- 買収したい事業のみを選択的に取得できる
- 簿外負債や偶発債務などのリスクを回避できる
デメリット
- 手続きが煩雑で、時間やコストがかかる
- 従業員や取引先との契約を個別に引き継ぐ必要がある
3. 会社分割
概要: 買収対象企業を分割し、その一部または全部を別の会社に承継させるスキームです。
メリット
- 事業譲渡と同様に、買収したい事業のみを選択的に取得できる
- 不要な事業を切り離すことができる
デメリット
- 手続きが非常に煩雑で、時間やコストがかかる
- 債権者や株主との調整が必要になる
4. 合併
概要: 複数の会社を1つの会社に統合するスキームです。
メリット
- 経営資源を集中し、事業規模を拡大できる
- シナジー効果を創出しやすい
デメリット
- 手続きが煩雑で、時間やコストがかかる
- 従業員や企業文化の統合が難しい場合がある
上記4つのスキームのうち一般的に使用されるのが①株式譲渡と②事業譲渡の2つになります。ここでは株式譲渡と事業譲渡をより具体的に説明させていただきます。
当社では事業承継の選択肢を増やすための「出口戦略」診断も企画しておりますのでご参加ください。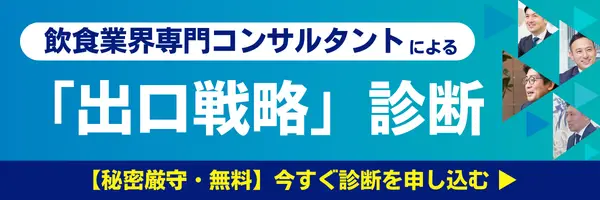
食品業界:株式譲渡のスキームについて
法人全体を譲渡するM&Aにおいては株式譲渡のスキームが選択されることが一般的です。株式譲渡においては、売り手企業の株式を買い手企業が取得することで、企業を統合します。
図:株式譲渡によるM&Aのスキーム

- 株式譲渡の成立には、まずは譲渡側と譲受側が株式譲渡契約を締結します。この契約には、株式譲渡の条件や価格、決済日などが含まれます。
- 取締役会および株主総会で株式譲渡の承諾決議を行います。
- 譲渡側は株券(株券発行会社の場合)、株式名義書換請求書兼株主票、会社実印、印鑑証明書、銀行印、通帳、鍵などを準備します。
- 決済日を迎えると、譲受側が譲渡側に対して株式の譲渡価格を支払います。支払いが完了すれば、株式譲渡は完了です。
譲受側は株式の所有者となり、譲渡側は株式の所有権を失います。また、取締役などの変更登記が必要な場合は登記申請を行います。株式譲渡は株主が変わるだけで、ほかは大きく変わりません。
食品業界:株式譲渡における譲渡側のメリット
譲渡側からすれば株式の譲渡対価が直接入ってくることはメリットと言えます。また、税金の面でもメリットがあります。たとえば相続や贈与の場合、課税金額に応じて相続税や贈与税が最大55%かかります。片や個人の場合、譲渡益に対する所得税、住民税で20.315%の税率となり手元に残る資金に違いがあります。
食品業界:事業譲渡のスキームについて
譲渡側が、企業内において複数の事業を運営する中で、一部事業だけを譲受側に譲渡する取引を「事業譲渡」と言います。承継する事業において必要な資産、負債、各種契約(賃貸借 契約、リース契約等)、従業員等を譲受側が譲り受けることで、譲渡日から、契約した一部事業だけを、譲受側が譲り受け、運営を引き継ぐことになります。
図:事業譲渡によるM&Aのスキーム

当社では株式譲渡スキームの相談をはじめ、適切な譲受方法などを検討するための「出口戦略」診断も企画しておりますのでご参加ください。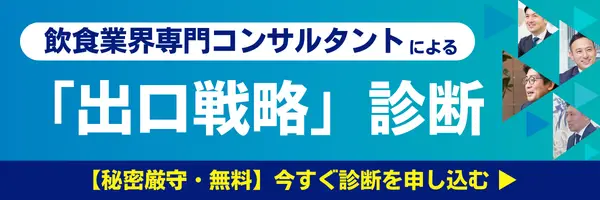
事業譲渡における譲受側のメリット
譲受側メリットとしては、不必要な、そのほかの事業の承継を行わないことが挙げられます。また、譲渡側が有する譲渡対象外の資産や負債等については、その責任の所在を区分することで、一定程度、想定していないリスク(簿外債務等)を引き継いでしまうことを回避することができます。
但し、各種契約(賃貸借契約、リース契約等)や、従業員との雇用契約については、個別に承諾を取得していく必要があり、株式譲渡のスキームと比較して、手続きに時間を要する可能性があります。 しかし、許認可関係の引継ぎが少ない場合や、従業員数、取引先との契約数が限定的な事業においては、比較的シンプルに、一部事業だけを、譲渡することが出来るスキームであることから選択肢のひとつとして、ご検討ください。
食品業界特有のM&Aスキームの注意点
食品安全規制: 食品業界は、食品安全基本法や食品衛生法などの人々の健康と安全に直接関わるため、他の業界に比べて厳しい食品安全規制が設けられています。M&Aを行う際には、買収対象会社のコンプライアンス状況や品質管理体制を十分に調査する必要があります。
1. 食品衛生法に基づく許可・届出
- 営業許可: 食品を製造・加工・販売する事業者は、原則として都道府県知事の許可が必要です。
- 許可業種: 食品の種類や製造方法によって、32種類の許可業種に分かれています。
- 許可基準: 施設・設備、衛生管理体制、食品衛生責任者の配置などが基準となります。
- 営業届出: 一部の業種では、許可ではなく届出で営業が可能です。
- 届出対象業種: 食品の販売業、食品の容器包装の製造業などがあります。
- 食品衛生責任者: 食品を製造・販売する施設には、食品衛生責任者を置く必要があります。
- 資格: 食品衛生責任者養成講習会を修了した者、栄養士、調理師などの資格を持つ者がなれます。
2. その他関連法規に基づく許可・届出
- HACCP(ハサップ): 食品の製造工程における衛生管理システムです。HACCPを導入する事業者は、都道府県知事に届出を行う必要があります。
- ISO22000: 食品安全マネジメントシステムの国際規格です。ISO22000を取得する事業者は、認証機関の審査を受ける必要があります。
3. 食品の種類・製造方法に応じた許可・届出
- 乳製品: 乳製品の製造・販売には、特別な許可が必要です。
- 食肉: 食肉の処理・販売には、と畜場法に基づく許可が必要です。
- 冷凍食品: 冷凍食品の製造・販売には、冷凍食品製造業の許可が必要です。
- 添加物: 食品添加物の製造・販売には、食品衛生法に基づく許可が必要です。
4. 許認可に関する注意点
許可・届出の必要性: 食品を製造・販売する事業者は、必ず必要な許可・届出を確認する必要があります。 許可基準: 許可を得るためには、施設・設備、衛生管理体制、食品衛生責任者の配置などが基準に適合している必要があります。
食品業界では上記の通り、許認可の引継も大きなポイントになります。また、食品業界では一部事業の譲渡(事業譲渡)も他の業界と比べて数多く行われております。事業譲渡は許認可の再申請など複雑なところもありますが、株式会社船井総研あがたFASでは株式譲渡、事業譲渡どちらの提案も可能で数多くの実績があります。
下記一部成約事例抜粋―――――――――――――――――――
◆【関東】 製パン業
スキーム:事業譲渡
年商規模:5,000万円~6,000万円 営業利益:500万円
譲渡価格:1,500万円
譲渡理由:事業に対する将来性に不安があり、事業再編の目的で譲渡
◆ 【関東】 総合食品小売業
スキーム:株式譲渡
年商規模:3億円~5億円 営業利益:1,000万円
譲渡価格:500万円
譲渡理由:創業者が長年経営してきたが、後継者不在のため譲渡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
食品・飲食業界のM&Aスキームは多種多様です。ご自身の運営形態、ご希望に合わせながらスキームを組み立てていく必要があります。食品・飲食業のM&A専門サポートチームがある当社では食品・飲食業専門のコンサルタントが、業界特化型M&Aのサポートをさせていただいております。お話をお伺いしながら現実的な出口戦略を一緒に検討することが出来ます。是非一度お問い合わせください。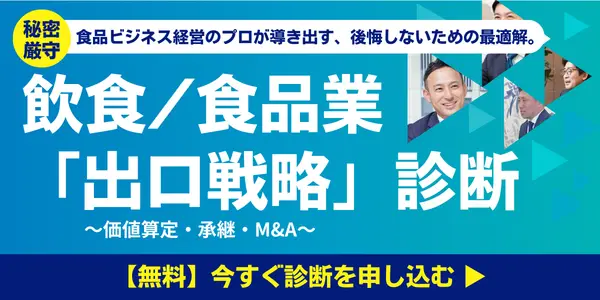
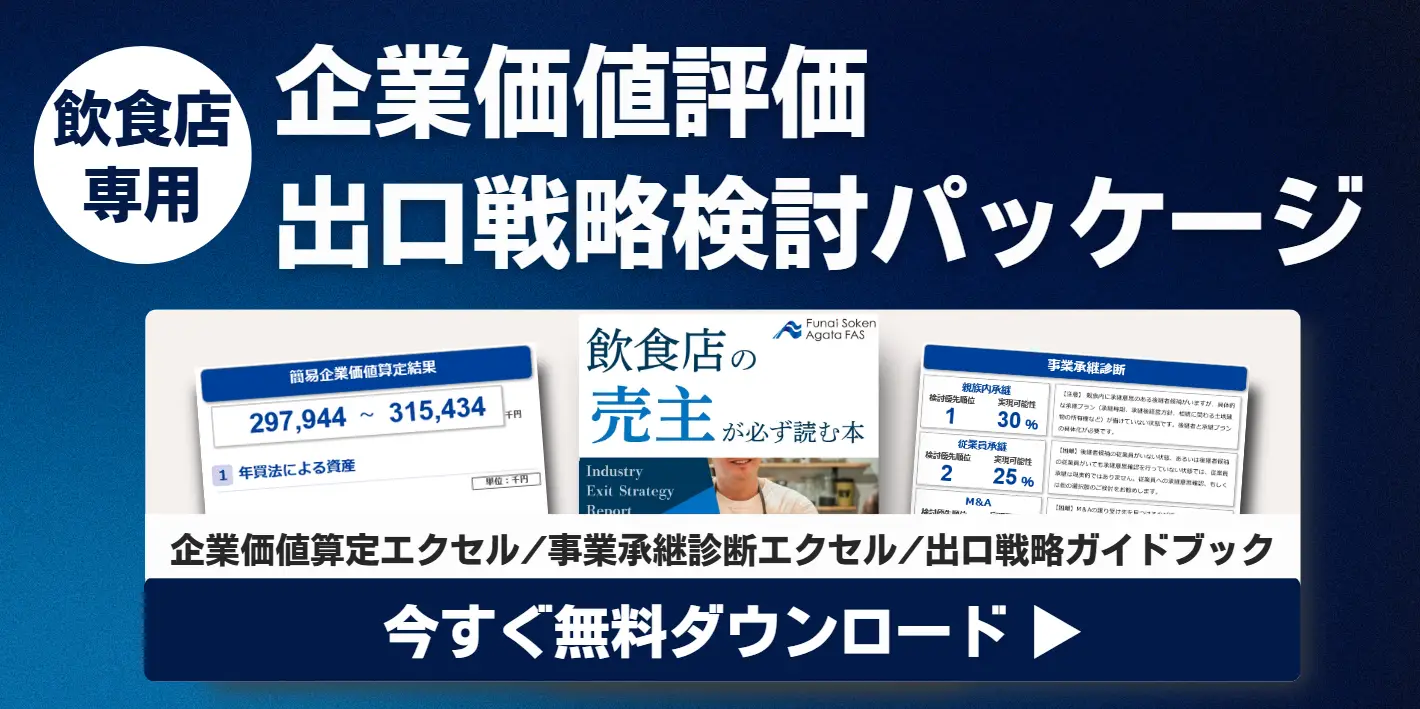

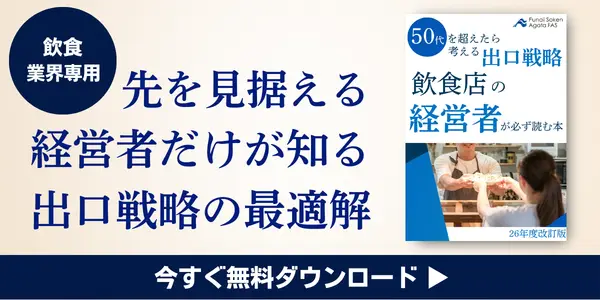
食品・飲食業のM&Aについてはこちらからご確認ください。
1.飲食/食品業界M&AのTOP
2.食品業界の2024年M&Aの振り返り
3.食品製造業界M&Aに関するメリットとデメリット
4.知っておきたい!食品業界のM&Aのポイント
5.食品業界のM&Aで使われる譲渡スキーム
6.食品製造・食品卸業を売却する際に検討しておくべき情報
7.食品業界のM&A事例