近年、食品業界ではM&Aが活発化しています。しかし、M&Aがテレビや新聞に頻繁に出てくるようになったのはここ最近かと思います。M&Aという言葉は知っているけど、実際どのようなものなのかをわかりやすく説明したいと思います。
「まだ先のこと」と考えているうちに、選択肢が狭まってしまうかもしれません。今年以降のさらなる採用難・競争激化に備え、今から「攻めの出口戦略」を検討しませんか?具体的な検討ツールのダウンロードや、専門家への出口戦略の相談を通じて、納得感のあるリタイアへの準備を今から始めることができます。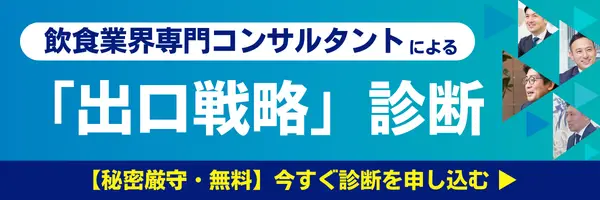
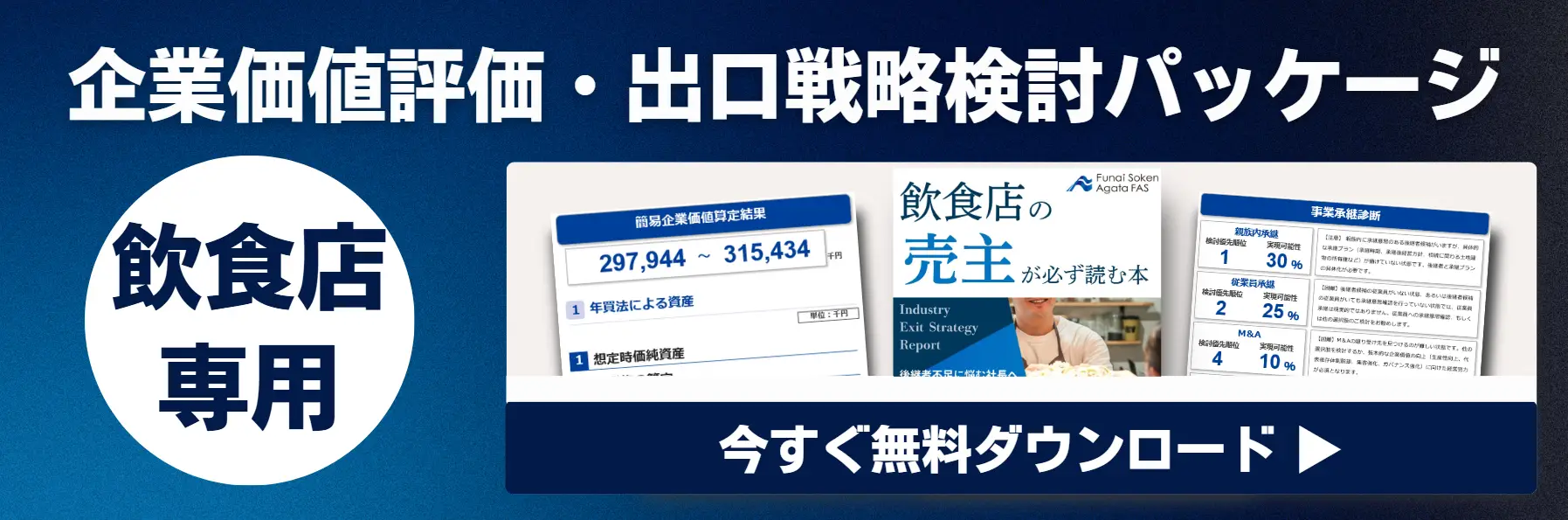
M&Aとは?
M&Aとは、「Mergers and Acquisitions」の略で、日本語にすると「企業の合併・買収」と訳されます。簡単に言うと、複数の企業が一つになること(合併) や、ある企業が他の企業の経営権を取得すること(買収) を指します。
M&Aには、大きく分けて以下の3つの種類があります。
- 水平型M&A: 同業種・同業態の企業同士のM&A
- 垂直型M&A: 川上・川下の企業同士のM&A(例:食品メーカーと小売業)
- コングロマリット型M&A: 異業種・異業態の企業同士のM&A

水平型M&Aとは?
水平型M&Aとは、同業種に属する企業同士が合併または買収を行うことです。競合他社を吸収合併することで、市場シェアの拡大やコスト削減、技術・ノウハウの共有などを目的として行われることが多いです。例えば、業界は違いますが最近話題となったホンダ自動車と日産自動車の経営統合に関する話題などがあります。結果的に統合には至らなかったですが、業界を揺るがす大きな話題となりました。
食品業界でも同じようなM&Aは行われており、原価高騰の影響から経営が行き詰った年商規模約10億円の食肉加工業の企業を地域トップクラスの食品製造業の企業が地域内のシェアアップ、工場の稼働率向上、統合による経費効率化の観点からM&Aに至ったケースがあります。しかし、水平型M&Aは、企業の成長戦略として有効な手段の一つですが、同じ業界だからこそ双方の企業文化の違いによる統合の難しさなどの課題も存在します。
垂直型M&Aとは?
食品業界における垂直型M&Aは、川上(原材料調達、製造)から川下(販売、流通)までのバリューチェーン全体の効率化を目指した手法です。
垂直型M&Aの主な目的
- サプライチェーンの効率化: 原材料の安定確保、製造・販売・物流の一貫管理によるコスト削減、リードタイム短縮
- 品質管理の強化: 原材料の品質管理、製造工程の可視化による品質向上、トレーサビリティ確保
- ブランド力の向上: 自社ブランドの育成、販売チャネルの拡大によるブランド力の向上
- 市場シェアの拡大: 川上から川下までを統合することで、競争優位性を確立し、市場シェアを拡大
- 新規事業への参入: 川上または川下の事業を買収することで、新たな事業領域へ参入
食品業界の垂直型M&Aでわかりやすいのが6次産業化を目指したM&Aの取り組みです。特に大手小売企業の戦略として自社で一次産業(生産)と二次産業(加工)を保有し、PB商品として安く販売しています。
当社では、事業承継の選択肢を増やすための「出口戦略」診断も企画しておりますのでご参加ください。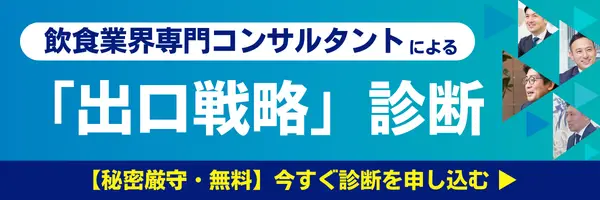
コングロマリットM&Aとは?
コングロマリット型M&Aとは、既存事業とは異なる多角的な事業分野に進出している企業が、それぞれの事業を強化・拡大するために、他の企業を買収・合併するM&Aの手法です。
コングロマリット型M&Aの主な目的
- 事業の多角化: 新規事業への参入や、既存事業の強化を通じて、事業ポートフォリオを多様化し、リスク分散を図る。
- シナジー効果: 異なる事業分野の企業を統合することで、相互に連携し、新たな価値を生み出す。
- 規模の拡大: M&Aを通じて企業規模を拡大し、市場での競争力を高める。
コングロマリット型M&Aは食品業界では大手を中心に行われています。例えば食肉加工業の企業が2000年初頭におきたBSE問題の際には、牛肉製品への依存度を減らすため、豚肉、鶏肉、加工食品など、他の製品の開発・販売を強化する目的でのM&Aも活発に行われました。
食品業界のM&Aの特徴とは?
食品業界の市場規模は約115兆円と日本国内の産業の約10%の市場規模を占めています。また、食品業界は幅広く農林漁業から食品製造/加工業、食品流通業、外食産業まで含まれています。その分、同業種だけでなく上記で記した垂直型M&Aも活発化しやすい構造となっています。また、昨今の原価高騰の影響は中小企業に大きな影響をもたらしており、値上げ交渉を行わないと経営が成り立たない企業も多くあるかと思います。実際に私がお付き合いしている企業でも既存の取引先に値上げ交渉に回る日々が続いているそうです。
そうした厳しい外部環境の中、将来の先行き不安からモチベーションの維持が難しいと嘆く経営者を多く見てきました。このような厳しい環境を自社だけで改善することは難しく、安定した大手企業と一緒に再成長させたいと話す経営者も多くいます。M&Aは様々な経営課題を解決し、企業の再成長を図るうえで1つの選択肢となり得ます。しかし、M&Aの市場が活発化している中で昨今ニュースにも取り上げられているように問題も発生しています。M&Aは大きな決断となる分、検討される方は十分に知識を得る必要があります。また、専門知識が必要な分野でもあるため、一人で悩まず相談できる相手を持つことをおすすめします。
船井総研あがたFASはグループ会社の船井総合研究所出身の経営コンサルタントも数多く在籍しています。M&Aに限らず、業績アップや組織に関する悩みにも親身に対応するコンサルタントが多いのも弊社の特徴です。弊社のモットーである経営“者”に寄り添ったアドバイス、経営“者”の成功を実現するためのサポーターとして、悩みごとがある方はぜひ、弊社までお問い合わせください。
食品・飲食業のM&A専門サポートチームがある当社では食品・飲食業専門のコンサルタントが、業界特化型M&Aのサポートをさせていただいております。お話をお伺いしながら現実的な出口戦略を一緒に検討することが出来ます。是非一度お問い合わせください。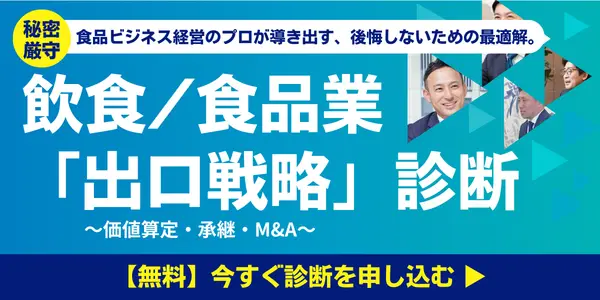
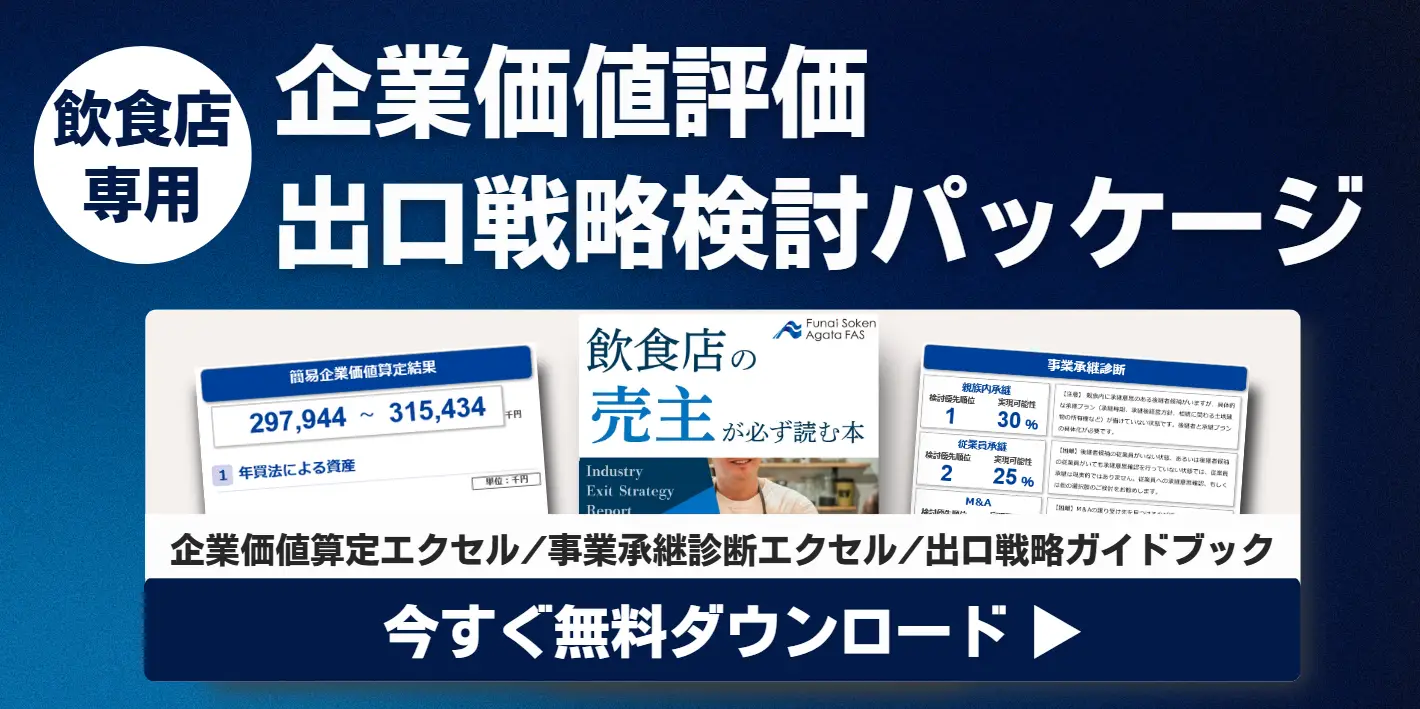

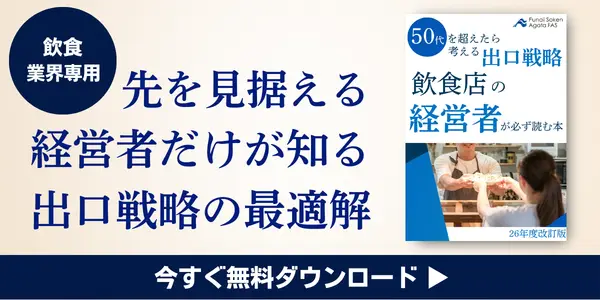 食品・飲食業のM&Aについてはこちらからご確認ください。
食品・飲食業のM&Aについてはこちらからご確認ください。
1.飲食/食品業界M&AのTOP
2.食品業界の2024年M&Aの振り返り
3.食品製造業界M&Aに関するメリットとデメリット
4.知っておきたい!食品業界のM&Aのポイント
5.食品業界のM&Aで使われる譲渡スキーム
6.食品製造・食品卸業を売却する際に検討しておくべき情報
7.食品業界のM&A事例