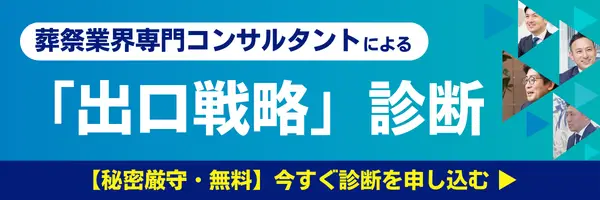いつもお読みいただきありがとうございます。 近年、葬祭業界ではM&Aが急速に活発化しています。人口減少や葬儀の小規模化など、環境が激変する中で、M&Aは事業継続や成長のための重要な選択肢となりました。しかし、この業界特有の商習慣や地域性を無視して進めることは、大きなリスクを伴います。
「まだ先のこと」と考えているうちに、選択肢が狭まってしまうかもしれません。今年以降のさらなる採用難・競争激化に備え、今から「攻めの出口戦略」を検討しませんか?具体的な検討ツールのダウンロードや、専門家への出口戦略の相談を通じて、納得感のあるリタイアへの準備を今から始めることができます。
【葬儀社専門「出口戦略」診断】自社の現状を整理し、最適な承継の選択肢を導き出す
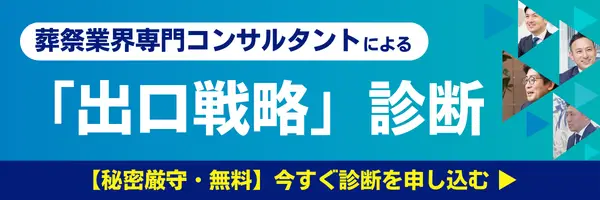
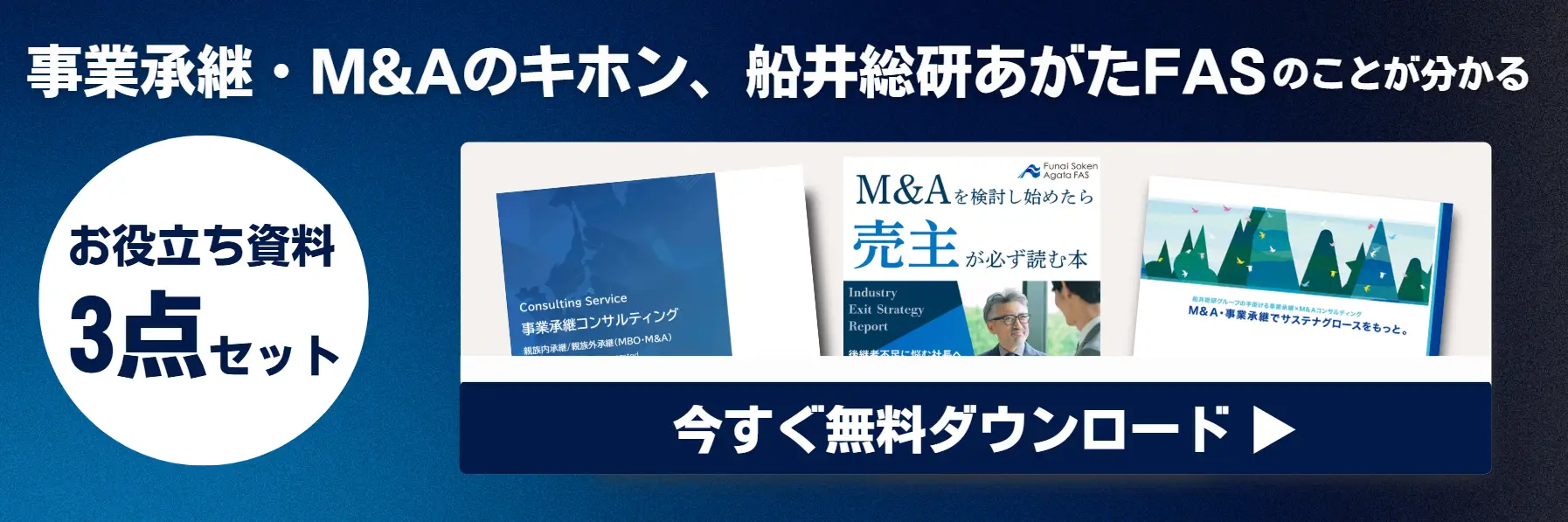 本コラムでは、譲り受け手と譲渡オーナーの双方が押さえておくべき成功の鍵を詳しく解説します。
本コラムでは、譲り受け手と譲渡オーナーの双方が押さえておくべき成功の鍵を詳しく解説します。
近年、葬祭業界ではM&Aが活発化しています。人口減少や高齢化、葬儀の小規模化など、業界を取り巻く環境が大きく変化する中で、M&Aは事業の継続や成長戦略として注目されています。しかし、葬祭業特有の事情を考慮せずにM&Aを進めると、期待した効果が得られないばかりか、予期せぬトラブルに発展する可能性もあります。
本コラムでは、葬祭業のM&Aを成功させるために、譲り受け手と譲渡オーナーの双方が押さえておくべき重要なポイントを解説します。
1.M&A成功のポイントはビジネスモデルを正しく理解すること
葬祭業のM&Aを成功させるためには、まず葬祭業のビジネスモデルを正しく理解することが不可欠です。葬祭業は、地域密着型のビジネスであり、顧客との信頼関係が非常に重要です。また、葬儀の形態は、地域や顧客のニーズによって大きく異なります。
葬祭業のビジネスモデルの特徴
地域密着型
地域住民との信頼関係が重要であり、地域の慣習や文化に精通している必要がある。市区町村をまたぐと慣習が異なることもあります。
小商圏ビジネス
葬祭業は車5分、10分が商圏となります。車5分、10分にどれだけの人口が住んでいるかがビジネスの成功のカギを握ります。
消費者が葬儀社を選ぶポイント
消費者が葬儀社を選ぶ理由トップ3は「近いから」「知っていたから(過去、親族や親戚が葬儀を行ったから)」「会員に入っているから」となります。ただし、都心部や高度成長期に発展してきた市区町村においては、「ホームページの依頼」が年々増加する傾向にあります。
小規模化ニーズへの対応
葬儀の形態は近年「家族葬」が中心となり、「一日葬」「直葬(火葬式)」の割合も増加してきており、式場の形態も含めニーズに合わせた展開が重要になって来ています。
オペレーション
葬儀社はそれぞれの会社によってオペレーションが異なります。オペレーション次第で生産性が大きく変わるため、現状がどのようなオペレーションを行っており、どこに改善の余地があるのかを見極めることが非常に重要です。
これらの特徴を踏まえ、M&Aの目的や戦略を明確にすることが、成功への第一歩となります。
一般的なM&Aの目的と戦略
事業規模の拡大
M&Aによって、事業規模を拡大し、スケールメリットを追求することができます。
新規市場への参入
M&Aによって、新たな地域や市場へ参入し、事業領域を拡大することができます。
サービスの拡充
M&Aによって、新たなサービスやノウハウを取り入れ、顧客満足度を向上させることができます。
後継者問題の解決
後継者不足に悩む企業が、M&Aによって事業承継を実現することができます。
2.葬儀社をM&Aで譲り受ける時に気を付けるべきこと
葬儀社をM&Aで譲り受ける際には、以下の点に注意が必要です。
譲受側の注意点
デューデリジェンスの徹底
- ビジネス、財務・税務や法務、労務など、多岐にわたるデューデリジェンスを実施し、リスクを把握する必要があります。
- ビジネスデューデリジェンスにおいては今後の事業発展余地がどの程度あるのか、競合がどのような企業で今後の戦略はどうなっているのか等を調べる必要があります。
- 財務・税務デューデリジェンスにおいては、過去、どのような処理を行ってきているか、税務リスクは内科のチェックを行います。葬儀社は各社、料理や生花などの外注している商品の売上処理が異なるケースがあります。
- 労務デューデリジェンスで特に見なければいけないのが残業代の未払いがないかがポイントになります。葬儀業は24時間365日商売ですので、夜間の待機に関する考え方が各社異なります。
- 法務デューデリジェンスでは、特に式場が建築基準法に基づいて建てられているかを見る必要があります。
従業員の処遇
従業員の雇用条件や処遇を明確にし、不安を取り除くひつようがあります。特に葬儀社は従業員がいなければ成り立たない商売ですので、従業員のケアは譲り受けて、譲渡オーナー両者が協力してフォローしなければなりません。
顧客との関係性
譲渡側の顧客との関係性を維持し、信頼を引き継ぐことが重要です。顧客との関係性が維持できないのであればM&Aでなく、新規出店を選んだ方が得策といえるでしょう。また、屋号を大幅に変えると顧客離れが進む可能性があるので慎重に考える必要があります。
地域の慣習や文化
譲受側の地域における慣習や文化を理解し、尊重する必要があります。特に火葬のタイミングがエリアによって異なるので気を付ける必要があります。また、宗教者とのコミュニケーションを密にとる必要がある地域もあるので、地域特性に合わせた対応が必要です。
シナジー効果
M&Aによるシナジー効果を最大限に発揮できるよう、統合プロセスを綿密に計画していきましょう。シナジーを生むために何をすべきかは、基本合意後、デューデリジェンスのプロセスに入った時点で、譲渡オーナーとともに話をしながら事業計画を立てることがおすすめです。(船井総研あがたFASでは必ず、デューデリジェンスのプロセスの中でミーティングの機会をもうけるようにしております)
上記に記載していることは、M&A後の事業運営に大きく影響するため、慎重に対応する必要があります。
3.葬儀社をM&Aで譲渡する時に気を付けるべきこと
葬儀社をM&Aで譲渡する際には、以下の点に注意が必要です。
譲渡側の注意点
企業価値の評価
適正な企業価値を算出し、譲渡価格を決定する必要があります。ただし、企業価値はどこが譲り受け手になるかによってシナジーが大きく変わる業界ですので、譲り受け手によっては当初の期待していた価値よりも高く条件を提示してくれる企業もあります。
相手方(譲り受け手)の選定
何を重視して譲り受け手を選ぶのかも重要となってきます。企業価値を高く評価してくれる先を選ぶのも一つの選択肢となります。一方で、自社の企業文化や理念に共感し、従業員や顧客を大切に譲り受け手として選ぶケースもあります。株主とM&Aアドバイザーとでどの点を重視して選んでいくかを検討していきましょう。
従業員への説明
従業員に対しての説明タイミングはM&Aが決定した直後となります。その際にはM&Aの目的や今後の処遇などを丁寧に説明し、理解を得る必要があります。場合によっては、全員への発信ではなく1対1で一人一人にお伝えしていくケースもあります。譲渡後、オーナー社長が会社に残る、残らないで従業員の安心感が大きく異なります。株を譲り渡した後もそのまま残るケースも多くあります。
取引先への説明
取引先に対しては、M&A成立後に案内状を出すのが一般的です。取引先も地域密着であることが多いので、取引先は継続的にお付き合いするケースも多くあります。ただし、エリアが被る企業とのM&Aの場合は取引先が変更となるケースも稀にあります。
秘密保持
M&Aに関する情報を外部に漏らさないよう、秘密保持契約を締結し外に情報が漏れないように慎重に進める必要があります。従業員が知ってしまった場合、不安になるケースもありますし、取引業者から業界へ噂が回ってしまうこともあります。M&Aはとてもナイーブな情報になりますので取り扱いを十分に注意する必要があります。
譲渡後も、従業員や関係会社、顧客との関係性を維持できるよう、誠実な対応が求められます。
まとめ
葬祭業のM&Aは、事業の継続やさらなる成長にとって極めて有効な手段です。しかし、成約をゴールにするのではなく、その後の持続的な発展に繋げるためには、特有のビジネスモデルに基づいた慎重な準備が欠かせません。
自社のポテンシャルを正しく把握し、主導権を握った経営判断を下せるうちに、まずは診断レポートで貴社の「戦略の現在地」を確認することから始めてください。
葬祭業のM&A専門サポートチームがある当社では葬祭業業専門のコンサルタントが、業界特化型M&Aのサポートをさせていただいております。お話をお伺いしながら現実的な出口戦略を一緒に検討することができます。是非一度お問い合わせください。
【葬儀社専門「出口戦略」診断】経営の主導権を握れるうちに、まずは可能性の確認から
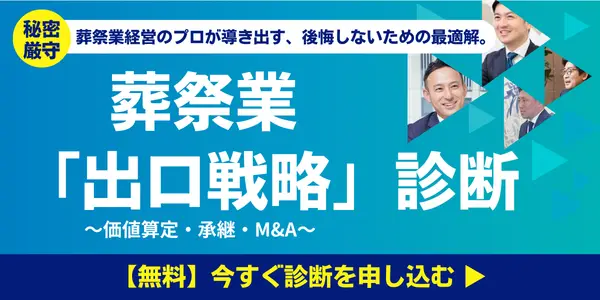
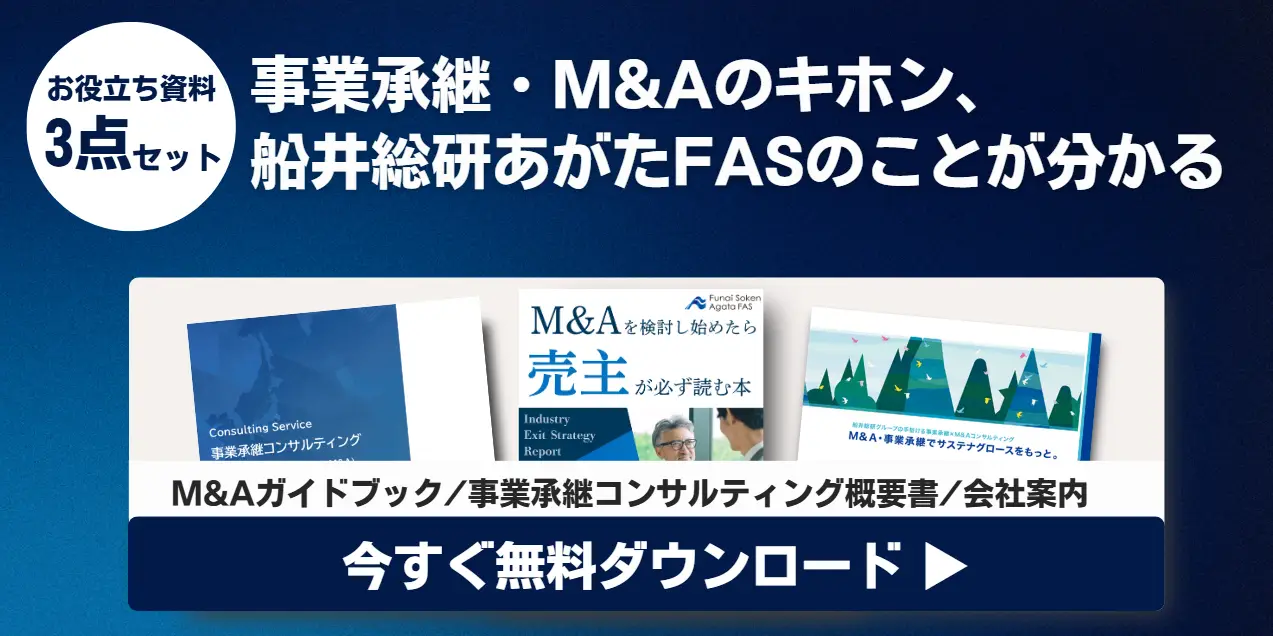
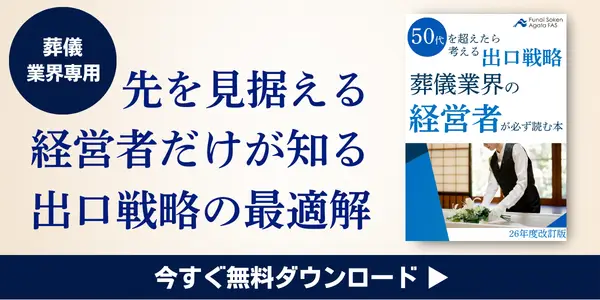 葬祭業のM&Aについてはこちらからご確認ください。
葬祭業のM&Aについてはこちらからご確認ください。
1,葬祭業M&AのTOP
2,葬儀業界M&A:2024年以降のM&Aの今後・ポイント・動向を解説
3,葬祭業M&Aのメリット・デメリット
4,葬儀社を売却する際に検討しておくべき情報
5,葬祭業M&A活発化の背景と事例